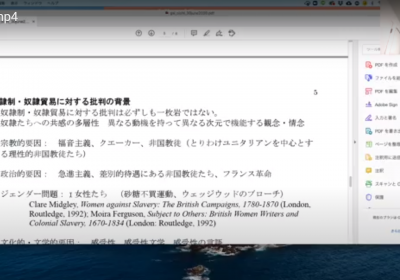【参加記あり】「グローバル・スタディーズの課題」シリーズ第3回「共感とチャリティの文化史研究とグローバル化時代の課題」

グローバル・スタディーズ・セミナーのご案内
【タイトル】「共感とチャリティの文化史研究とグローバル化時代の課題」
【日時】2020年6月30日(火)14:55-16:40
【場所】Zoomミーティング
【スピーカー】大石和欣 東京大学大学院総合文化研究科教授(言語情報科学専攻)
【要旨】
近代イギリスにおいて、貧困や劣悪な生活環境、あるいは奴隷制が深刻な社会・政治問題として認知され出したのは18世紀後半のことである。16世紀以来の救貧法への批判が高まり、さまざまな篤志に基づくチャリティが活発になり、奴隷貿易廃止運動も北米のクエーカーたちの行動と呼応しながら興隆する。そこに垣間見えるのは、社会的に抑圧された存在への共感と救済を謳う言説群である。それらは歴史的な状況のなかで、同時代の道徳・宗教思想に感化されながら醸成された心性を示唆している。こうした心性研究はイギリス国内の状況のみならず、グローバルな視野を通して再考される必要性が高まっている。
17世紀末から顕著になりはじめた金融資本の流動化、商工業の発展、そして消費の活性化、さらにはそれらを促進した北米、西インド、インドを中心としたアジア、そしてアフリカ、オーストラリアやニュージーランドにおけるイギリスの覇権拡張によって、富はイギリス国内に蓄積されていくことになった。その一方で、移動する、あるいは都市に流入する労働人口の増加と、その結果としてあるいは飢饉発生に伴う救貧法の機能不全は、貧富の格差を社会において明瞭なものにしていくことになった。また、いわゆる三角貿易の一角を担っていた奴隷貿易は、イギリス国内に富を還流させながら、アフリカから奴隷を西インド諸島や北アメリカ南部におけるプランテーションに労働力として供給することで、奴隷制を帝国覇権の一部に組み込んでいった。そのことは貧困や奴隷制という問題が、資本・労働・モノ・情報のグローバルな流通という現代にもつながる文脈において考察すべきものであることを意味する。20世紀末までの貧困についての歴史研究は、国内における救貧法施行の実態や民間の篤志に基づくチャリティのあり方を同時代の社会状況のなかで精査することで、貧困問題の本質を解き明かそうとしてきた。しかし、21世紀における研究状況は、そうした狭量な視座を乗り越えて、グローバルな資本や労働、モノ、情報の移動を通して貧困や奴隷制といった問題が生じている構造にも着目する必要性を認識している。
この時代に困窮し、あるいは隷属的状況に甘んじる人びとに対する眼差しは、こうした歴史的状況のなかで培われていった。感受性の時代と言われる18世紀後半、共感や憐憫といった美徳が称揚され、機能しない救貧法への批判を伴いさまざまなチャリティが活発になる。啓蒙的な道徳思想においても「共感」は重要な概念として位置づけられていく。また、フランス革命が掲げた「自由」「平等」「博愛」の理想は、社会的弱者への眼差しが敗退する政治的な意味をよりいっそう複雑なものにすることになっていった。しかし、この「共感」やチャリティもまた、上述のグローバルな文脈のなかで再考することを迫られている。そのときに「共感」はどのような心性として位置づけることができるのであろうか。
【司会】
伊達聖伸(総合文化研究科 地域文化研究専攻)
【討論者】
國分功一郎(総合文化研究科 超域文化科学専攻)
田辺明生(総合文化研究科 超域文化科学専攻)
馬路智仁(総合文化研究科 国際社会科学専攻)
【言語】日本語
【問い合わせ先】グローバル・スタディーズ・イニシアティヴ(GSI)事務局
「グローバル・スタディーズの課題」シリーズ:これまでのセミナーはこちらのページをご覧ください。
【セミナー参加記】
2020年6月30日(火)にグローバル・スタディーズ・セミナー「グローバル・スタディーズの課題」シリーズ第3回が開催され、大石和欣氏(東京大学大学院総合文化研究科教授)に「共感とチャリティの文化史研究とグローバル化時代の課題」と題してご講演頂いた。
初めに大石氏は、ジョージ・フロイド事件により世界中に広がっている反人種差別運動と、その背景としての奴隷貿易に関連して、それぞれの時代の中で感情が定義されていく様子を「共感」と「言語」の側面から考えていくと語った。分析概念として「チャリティ」を挙げ、まずチャリティの歴史を語る上では、エリザベス朝時代における「救貧法」が大きな軸となる。救貧法の背景には、アイルランドからの移民が急増した中で、教区に属していない人々を管理するという移民排斥・抑圧的な側面があった。やがて近代になり、救貧法だけでは貧しい人たちを救うことができない状況が生まれると、私的扶助の「チャリティ」が現れる。このためイギリスではチャリティを「混合経済」と呼ぶ。一方、植民地の獲得や海外貿易を通じた資本蓄積の過程の中で、奴隷貿易が形成されるに至った。
こうして、近代的な消費文化が生まれると共にチャリティは更に活性化し、1730-50年代には多くの慈善施設、特に啓蒙とチャリティが結び付いた慈善病院が盛んにつくられた。いずれにおいても純粋なチャリティではなく、帝国主義と結び付いた慈善であった。風紀改善運動も盛んになり、18世紀の半ばからは「感受性文学」が台頭した。ここで大石氏は、チャリティや共感が仁愛や博愛など様々な同義語的な表現となって特殊な文脈の中で使われたのが、18世紀における「共感」概念の面白さであると語った。例えば、フランシス・ベーコンが博愛を語りながら、caritasとgood willを同義語として扱う一方、フランシス・ハチスンの「普遍的仁愛」は、道徳的かつ政治的な概念である。またデイヴィッド・ヒュームが、仁愛やチャリティは極めて利己的な動機から行われると主張する一方、アダム・スミスにおいては、禁欲主義的で公平無私な共感が神が差配する「オイコノミア」のなかに位置付けられている。アダム・スミスが人間の干渉を否定した一方、貧困問題について人為的な補助や経済の構造改革が必要であるとする立場との間に論争が起こったことも語られた。
大石氏はチャリティの一つのジレンマとして、共感の対象問題を挙げ、家族、コミュニティ、地域、国家、世界にいる人々に対して、どこを共感の対象とすべきかという問題を巡る議論を紹介した。『百科全書』では地域や国家を超える「世界市民」の定義が紹介されているが、イギリスにおいては、合理的思考を持つユニタリアンは、人間が善なる存在として世の中を改善させるいう改革的な立場を取り、博愛こそが重要であると主張した。こうして18世紀末に、より身近なパトリオティズムとより圏域の広い博愛が対立し、定義の再構築が行われた。文学においても、奴隷貿易廃止に賛同する様々な言説が現れる中で「共感」が重要な概念として提示されたと大石氏は語る。「女性」に注目すると、共感の疼きをテーマにして奴隷に対する憐憫、同情、共感を喚起させる情感的な歌や、普遍的仁愛を背景に奴隷貿易を批判する詩が作られた。
地政学的な状況を考慮しつつ、奴隷制・奴隷貿易の問題を植民地批判というポスト・コロニアリズムの文脈で考えることが、グローバル化時代の課題であると大石氏は指摘した。奴隷貿易廃止運動についても、アメリカの独立などの地政学的な影響が不可避であったように、グローバルなコンテキストの中でこの問題を考える必要性がある。共感の「二律背反性」問題も挙げられ、共感そのものが道徳的な美徳ではなく、その対象と機能を再考する必要性も示された。ジョージ・フロイドの死を契機に反人種差別運動が世界的に広まり、奴隷制・奴隷貿易に関わった歴史的人物の銅像が破壊されているが、これは同事件に対する一つの共感であると言える。一方でグローバル化への反動として、移民排斥・民族主義についても共感が示されることから、現代は共感の多様性と多層性が揺れている時代であると大石氏は語った。
大石氏の議論に対し、同情・憐憫などの政治的な利用可能性や、イングランドにおける観念としての共感とチャリティの誕生背景、奴隷制・奴隷貿易の廃止要因は宗教や倫理的なものなのか、政治経済的なものなのかといった質問が寄せられた。また、反人種主義運動が繰り広げられる中で必要となる共感の形、そして共感の客体と主体を分ける一方的な共感の克服方法や関連する歴史的事例について白熱した議論が展開され、本セミナーは閉会した。
【報告:ハン・アラン(東京大学大学院総合文化研究国際社会科学専攻修士課程)】