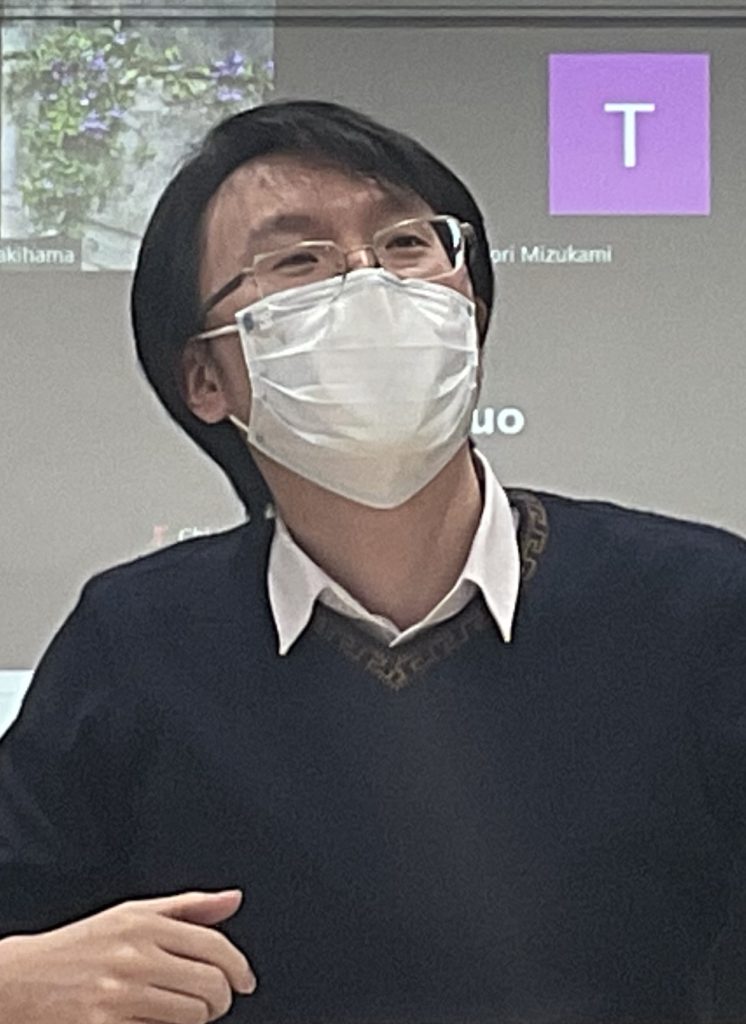【活動報告】東京⼤学グローバル・スタディーズ・イニシアティヴ(GSI)キャラバンプロジェクト「主権の諸条件」第4回ワークショップ
SovereigntyCaravan東アジア藝文書院(EAA)
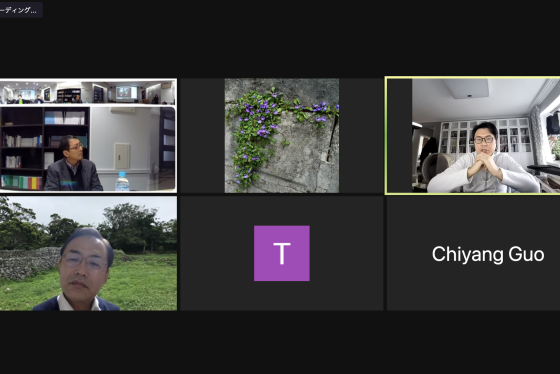
2021年12月18日、第4回となる東京大学GSIキャラバンプロジェクト「主権の諸条件」ワークショップがオンライン・対面併用のハイブリッド形式で開催された。第1回のジャック・レズラ氏(カリフォルニア大学リバーサイド校)、第2回のキム・ハン氏(延世大学)、第3回の汪暉氏(清華大学)に続き、今回は北京大学から章永楽氏をお迎えした。章氏は東アジア藝文書院設立当初から今日に至るまで、サマー・インスティテュートやUTokyo-PKUジョイントコースなど、さまざまな場面において本学と北京大学とのパートナーシップの深化に尽力してきたキーパーソンである。
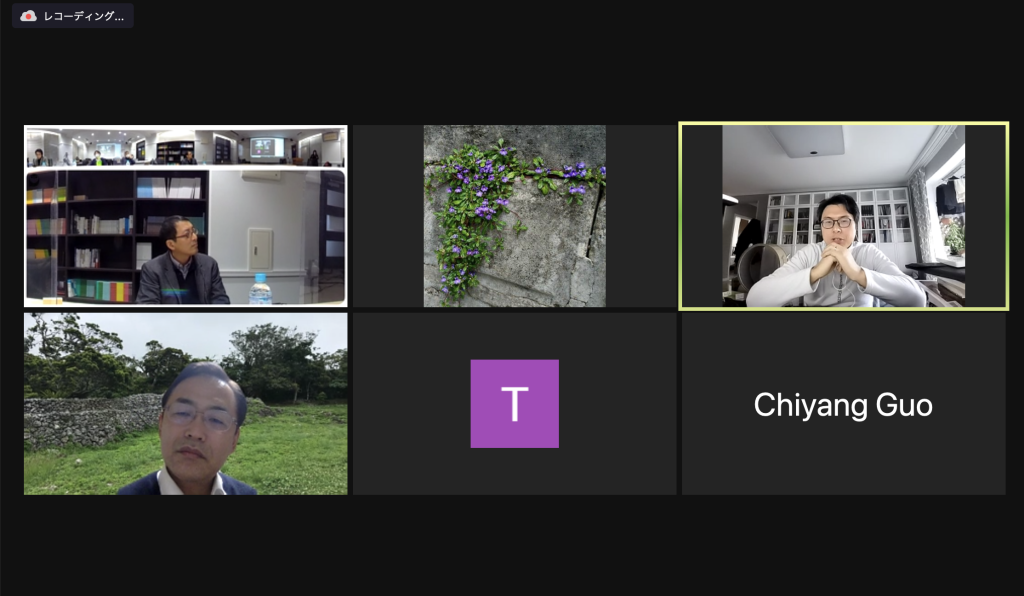
“Rethinking the Concept of ‘Imperial Sovereignty’ in the Age of Trade War”と題して行われた講演では、アントニオ・ネグリ=マイケル・ハートの『帝国』における議論を下敷きとして、昨今のグローバル化した世界における「主権」のあり方について批判的に検討がなされた。グローバリゼーションの進展によって、国民国家や、それにまつわる従来の国家主権は力を弱め、代わって超主権的な「帝国」が出現する。これに対抗するために「マルチチュード」に力を結集し新たな抵抗勢力のあり方を構想する、というのがネグリ=ハートの描いたある種の未来予想図であった。しかし現在実際に展開しているのは、国家主権の弱体化ではなく、ある種の強化なのではないか。章氏は国際政治における具体例に言及しながら、こうした根本的な問いを投げかけた。
章氏の熱のこもった講演に応えるように、キャラバンメンバーからも鋭い質問が複数提示された。例えば中島隆博氏(EAA院長)は、次のように問うた。中国を今日のグローバリゼーションと主権というディスコースの中にどのように位置付けることができるか。中国における「主権」をめぐる議論の系譜は現在の議論にどのように介入可能か。また、石井剛氏(EAA副院長)は、高山岩男の「世界史の哲学」や、大東亜共栄圏を構想した京都学派の諸議論に言及しつつ、こうした言説に孕まれる難題をどのように回避・克服することができるだろうか、と問いかけた。両氏の問いに対する章氏の応答、また、キャラバン主宰者である國分功一郎氏(東京大学)が展開した議論は、「主権」を新たな方向性において構想する一つの道筋を示した。そこで示されたキーワードは、(とりわけ第三世界を中心とした)インターナショナルな連帯、そして「開かれ(openness)」である。王欽氏(東京大学)が指摘したように、グローバリゼーションがどれだけ展開されようと、また、どれだけ国際情勢が変化しようと、アメリカに象徴されるような超主権的国家主権の力はますます凌駕的であるように見える。張政遠氏(東京大学)が言及したように、中国において中国的民主主義(Chinese democracy)とも言うべき概念あるいは実践が議論される中、一体どのような未来を構想することができるのだろうか?
今回のディスカッションを通して確認されたのは次のことである。日本も中国も、「アジア」と名指される空間のアクターである。しかし、わたしたちはこの「アジア」という空間を閉じられたものとして想定するべきではない。国民国家、あるいは主権には、影と光の両側面があるが、これらの概念に死を告げるにはまだ早く、依然として有効性を持っている。今必要なのは、内/外を強固に腑分けする「主権」ではなく、緩やかな連帯を可能とするような、いわば分有的主権(例えば中島氏が『危機の時代の哲学』(東京大学出版会、2021年)で論じたような)であるだろう。こうした思想実践を真に展開していくためには、白永瑞(『共生への道と核心現場』法政大学出版局、2016年)が論じたように、沖縄・台湾・香港・済州といった、主権と主権の挟間に過酷な生を与えられている「核心現場」という主体/場所からの視座が決定的に重要であろう。そこからは、例えば次のような問いが提示され得る——分有された主権というものが成立し得るとして、それは果たして軍事力と切り離すことが可能なものなのだろうか?この問いを徹底的に問わないのであれば、カール・シュミットが分割不可能な至高の権力として定義した「主権」を分有するという試みは、永遠のアポリアとして宙を浮遊し続けるだろう。しかし、絶対に不可能なアポリアを実現せんとする狂気にしか、変革を可能にする力は宿らないことも確かだ。思想とは、あるいは哲学とは、狂気の上に咲く花のようなものである(その花の力は底知れぬものであり、その力をどのような方向性に働かせ、次なる種を蒔こうとするかは、花を手にした者たち次第である)。今回の議論で言及された狂気の花々——シュミット、アガンベン、ネグリ=ハート、そして京都学派の哲学や、現代中国における諸議論——の上に、新しい花を咲かせ種を蒔くことができるような思想実践の場として、東アジア藝文書院が存在し続けることができれば、と思う。
報告者:崎濱紗奈(EAA特任研究員)
撮影者:伊野恭子(EAA学術専門職員)