【参加記あり】第1回グローバル・スタディーズ・セミナー 中村沙絵「「ケアするように書くこと」あるいは〈歌〉としての民族誌」
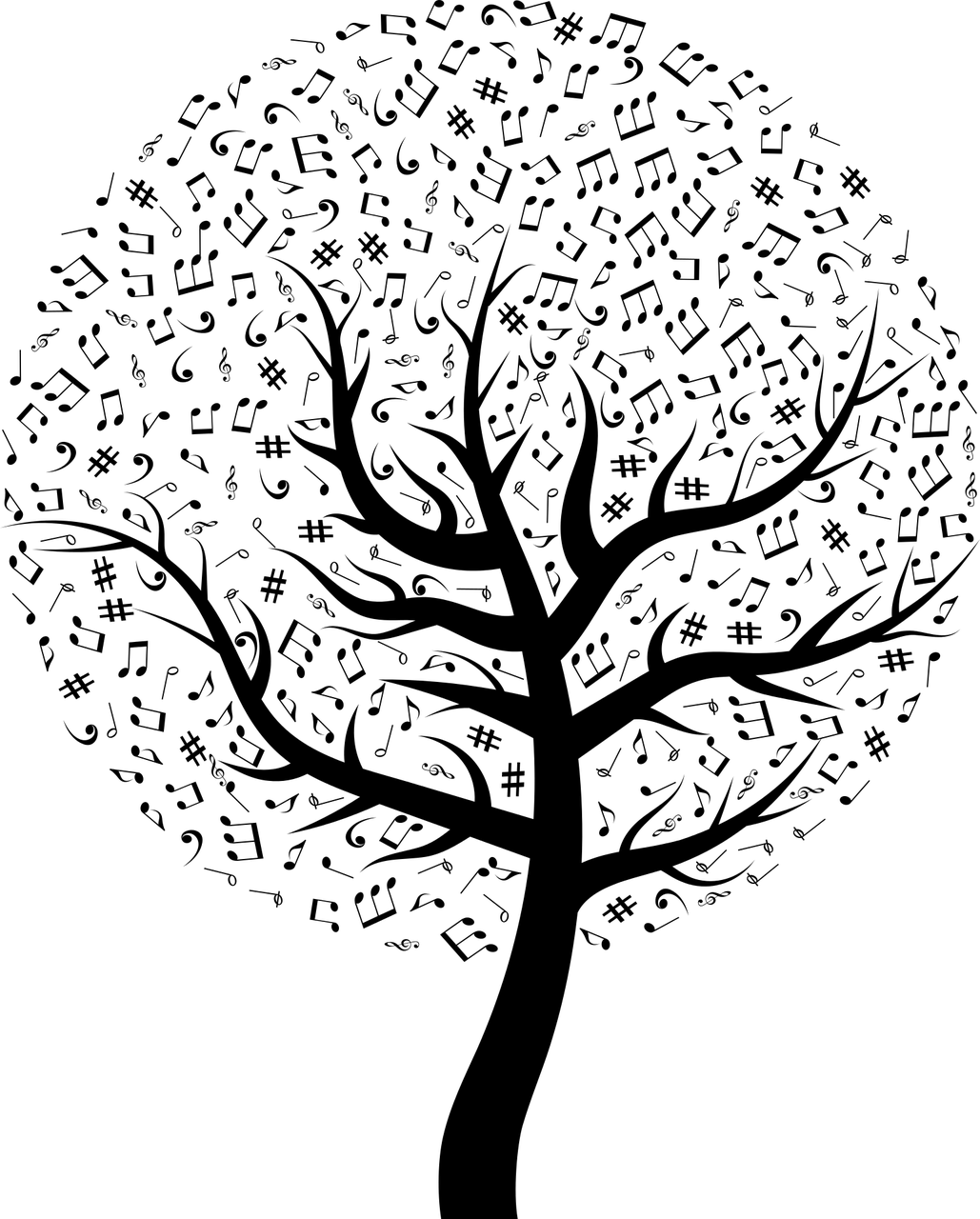
【日時】2023年10月26日(木)15:00~16:30
【司会】伊達聖伸(総合文化研究科地域文化研究専攻)
【コメント】國分功一郎(総合文化研究科超域文化科学専攻)
【コメント】塚原伸治(総合文化研究科超域文化科学専攻)
【言語】日本語
【開催場所】ウェビナー(要事前登録)
【要旨】あるものの考え方や価値観が特定の集団において間主観的に共有されているかどうかや、フィールドで繰り返し見られかどうか、といったことは、人類学者が長期のフィールドワークを通して明らかにすべき基本的な事柄とされる。しかし、曖昧さを排した確定記述の積み上げという規範にこだわれば、調査地の人々の語りや経験のうち、曖昧で確証のないものは省略されるか、真剣に受け止められないことにもなりうる。
私が2007年から2010年にかけてフィールドワークを行ったスリランカの養老院は、確定記述からこぼれるような、とらえどころのない現実に満ちみちた世界だった。そこでの老病死の現実は調査地の人たちにとって予期しないことの連続で、「あっけない」死や親族に顧みられない死の光景は間主観的に共有された文化的意味づけなど寄せつけないかにみえた。施設で最期を迎える人たちに付き添う若い女性スタッフたちは、入居者の姿を嘲笑し遠ざけようとしつつも、目の前の入居者に「なってしまう」近さにおいて看取りに従事していた。私自身もまた経験したように、そこは入居者とともに根本的な生の条件に曝される契機が潜んでいる場所だった。
明晰に確証できる事柄について曖昧さを排して書いてしまえば、フィールドで学んだ大事なものごとをとりこぼしてしまう——私にとって民族誌を書く(あるいは書き直す)営みとは、こうした直観にもとづく方法論の探究であり、それはまたままならない生を生きる入居者やスタッフたちの生きざまを厳密に論じる対象とするのでなく、ただ記述をとおして〈居場所を与える〉ような関わりに向けた試行錯誤でもあった。本発表では、この試行錯誤から導かれた民族誌の書き方についての道筋のひとつを、Lisa Stevensonの著作から着想をえつつ、「ケアするように書くこと」あるいは〈歌〉としての民族誌、という概念をてがかりに提示する。
【参加記】「信頼に足る民族誌」として一般的にイメージされるものがある。主観を交えず客観的に書くなどの「学術的な」作法に則ること、フィールドにおいて繰り返しにより確証された民族誌的事実を積み上げることで「確からしさ」を得ることなどが期待される。しかし、自身がフィールドに行き民族誌を書くとき、中村氏はそのような民族誌の書き方の困難や限界に直面したと言う。その経験が今回の発表のテーマに繋がっている。
中村氏はスリランカの老人施設「ヴァディヒティ・ニヴァーサ」を中心に、そこでフロアスタッフ見習いとして働く機会を得てフィールドワークを行なった。「シックルーム」と呼ばれる末期の入居者たちが過ごす部屋の担当になると、そこでの看取りのやり方へ違和感を持ったと言う。最低限の医療的介入、可能な限り食べさせる看護、同僚のフロアスタッフがときおり「こんなにして生きていても仕方がない」などと言うこと。自分にとって自然な「よい」「ケア」のイメージとの違いに迷いを持ち続けていた。
そんな中で、ディンギリアンマと呼ぶ、とある女性入居者を看取った経験が強い動揺をもたらした。当時のフィールドノートから、食欲を失っていた彼女が珍しく紅茶や食事を欲しがり、急いで準備して口に運んで食べさせたこと、その翌日の朝にディンギリアンマが亡くなったときのことが語られた。その急な死と目の前の光景に強く動揺し、だんだんと見聞きした事実を書き残すという自分の行為や存在の意味を見失ったと言う。
帰国後も迷いを抱え続ける中で、ふと志賀直哉の『城の崎にて』を読んだことで、自分の抱えていた問題に気づいたと言う。主人公がふと投げた石がイモリに当たり死んでしまう場面が紹介された。イモリを殺してしまった後、自分が生き残っていることに淡々と深い戸惑いを抱く主人公と自分の経験が重なり、親しみを覚えたと言う。
中村氏がそこで気がついたのは、フロアスタッフへの違和感を抱え、できるだけ入居者たちを「人」として見ようとしていた自分は、施設での老病死の現実を「声」や「ニーズ」として対象化することで受け入れているに過ぎなかったということ、また、ディンギリアンマの死にショックを受けて何をすべきか見失ったのは、彼女とともに「生の根本的な条件」に曝されたことで、対象化できていた足場を失ったからだということだった。
こうした経緯から、他者に曝されて生じた情動的経験を根本的な生の条件の顕れとして受け止め、何かを書く/実践することはできるか、という問いが生まれたと言う。その中で強く感銘を受け、書き方のヒントとなったのが、Lisa Stevensonによる民族誌Life Beside Itselfであった。
スティーブンソンはイヌイトの若者の自殺率増加について調査を行った。そこでは、カナダ連邦政府による国民化政策と医療サービスへの介入において、イヌイトが「対象化」「固定化」され、彼らの生死が「数値」として表層的に把握されていた。彼女が注目したのは、そのような状況の中で、イヌイトの若者たちが、不確かな存在の影(亡くなった友との夢での再会など)について迷いや躊躇いとともに語っていることだった。スティーブンソンは、死者とのそうした関係のあり方に、今ここにいないものへのケアと表面的な存在として見なされる彼ら自身へのケアのジェスチャーを見出した。
中村氏は、この<ケアするように生きる>という営みを「反復複製」するものとしての民族誌、というヴィジョンを得て、<ケアするように書くこと>について考えている。事実が曖昧になる瞬間や躊躇いの瞬間の経験を尊重すること、対象を何者かとして固定化して見ることなく、伴侶(companion)として想起すること、という二つの観点が示された。
そのようなただ声を聞いている存在を許容するように寄り添うあり方をスティーブンソンは「歌(song)」と呼ぶが、そうした<歌>としての民族誌があり得るのではないか。つまり、捉えどころのない存在に寄り添い、ともに交感できるような「余地」をつくりだす行為として民族誌を書くことを考えられるのではないか。中村氏はこうした考えの中で、モノグラフを書き直すことを考えていると言う。フィールドノートを見返し、「聞けていなかった」歌や声の存在に改めて気づいた、ということが語られ、発表は終了した。
発表に続いて、塚原伸治氏と國分功一郎氏からのコメントがなされた。民俗学を専門とする塚原氏は、民俗学を学問として組み立てることを目指しながらも大学の外で育てる余地を残した柳田國男と、歌人であり続けた折口信夫という民俗学の基礎を築いた二人について紹介し、「学問でありながら、学問的でないような」研究や記述のあり方と、大学という制度やそこでの教育について質問した。國分氏は、学者がどういう人間であるかと切り離すことのできない「芸」としての学問があり、そこには当事者研究に溢れているような「笑い」の瞬間があり得るのではないか、とコメントした
それらを受けて、中村氏は当時のフロアスタッフを訪ねた際に、大変だったけれどどうしてあんなに楽しかったんだろうという思いを聞き、その楽しさについて考えたことを語った。また、インゴルドやドゥヴルーが指摘するように芸術や研究者自身の主観は昔から学問の中に溢れていて、その観点から人類学やそのほかの学問を読み直すことができるのではないか、という応答もなされた。最後に、フィールドの経験を概念を用いて考察することの困難さについて参加者から質問があり、中村氏は、説明するための理論だけでなく「書く実践そのもの」を考えるための理論を探すことが助けになるのでは、と答えた。
自身の経験と思考の過程について率直に語った中村氏の発表を中心に、学問のあり方そのものについて深く考えることのできるセミナーであった。
【報告者:佐藤秀俊(教養学部3年)】
